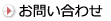- 2025年11月
- 2024年11月
- 2023年12月
- 2023年10月
- 2023年8月
- 2023年6月
- 2023年4月
- 2022年10月
- 2022年8月
- 2022年7月
- 2022年3月
- 2021年10月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年1月
- 2020年12月
- 2020年10月
- 2020年8月
- 2020年2月
- 2018年1月
- 2017年7月
- 2017年5月
- 2017年4月
- 2017年1月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年6月
- 2016年4月
- 2015年10月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2014年6月
- 2014年2月
- 2013年9月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年4月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月
| 大晦日 | 2012年12月31日 |
大掃除に
お餅つき、
お正月を迎える準備もひと段落して大晦日です。
夕食は林にお住まいの方が毎年
「屋台そば」をご馳走して下さいます。
子どもたちはというと、
帰省をしない児童が20人ほどいますので
のんびりとテレビを見ながら年越しをします。
最近は、年末=紅白歌合戦という方程式はなく
別の番組を見ながら、
自分の好きな歌手のときだけNHKという風景が当たり前になっています。
ゆく年くる年も
面白い番組をとチャネルをかえています。
今年の大晦日もおそらく
リモコンを持って色々と見比べるのだと思います。
| クリスマス | 2012年12月26日 |
24日のクリスマスイブ、25日とクリスマスと
子どもたちにとっては一大イベントです!
玉島学園にも24日の深夜
というより25日の未明
サンタクロースさんが子どもたちの枕もとにプレゼントを届けて下さいました。
25日は寒い朝でしたが、
どの子も、驚くほど早起きをしてプレゼントの確認です。
幼児さんは、お構いなしに包み紙を破ってしまい、
後になって部品がなくなっていたり
こわれていることも良くあることなのですが、
今年は大過なく朝を迎えることができたようです。
・
また、
クリスマスの時期にあわせて
個人や企業、地域の方からも多くの善意が寄せられます。
クリスマスの集いやオヤツでさっそくいただいたのは言うまでもありません。
文具については学齢に応じて手渡し
大切に上手に使うように話をしました。
皆さまからの心温まるプレゼントが
子どもたちの健やかな成長の糧となるように努力しなくてはと
気持ちを新たにした次第です。
皆さまにも幸多からんことを願いつつ。
| はだしのゲン | 2012年12月25日 |
12月19日
はだしのゲンの作者。
中沢啓治さんが広島市内の病院で肺がんで死去されました。
謹んでご冥福をお祈りいたします。
玉島学園の記事とは全く関係のないことなのですが
個人的な思いもあり、ブログに載せることをお許しください。
・
「はだしのゲン」は
週刊少年ジャンプに昭和48年(1973年)から
自身の体験を基に書かれ、
今では18カ国以上の国で翻訳され出版されています。
故手塚治氏の「宝島」に感動し
漫画家を志し
1963年(24歳の時)にプロデビューされた中沢さんは
自身が被爆者であることは隠して執筆活動を続けて来られていました。
転機が訪れます。
1966年
最愛の母親の遺骨が火葬で残らなかったことが
きっかけとなり「はだしのゲン」の執筆を決意されました。
「原爆はお袋の骨まで持っていくのか!」
ほとんど残らなかった遺骨に怒りを増幅させたそうです。
「はだしのゲン」の中で描かれた原子爆弾投下直後の惨劇
広島市内の様子は多くの読者に衝撃を与えました。
・
中沢さんは6歳のときに被爆、
父と姉、弟を亡くしつらく苦しい日々を
母と二人で生きてこられました。
今でこそ、原子爆弾による
さまざまな被害について
二次的な被害も含めて検証されてきていますが、
終戦直後は被爆者への差別や偏見も多かったのです。
今でこそ被爆者援護法が定められているのですが
1960年代は被爆者であることを公言すること自体、勇気のいることだったと思います。
お母さんの死という現実に直面したとはいえ
中沢さんの勇気に感服です。
そして、
中沢さんは恒久平和と核兵器の廃絶を願い
戦争の反省と
原子爆弾の脅威(非人道的な無差別攻撃)を
ゲンをとおして訴えかけてこられました。
来夏には原画など寄贈された原爆資料館で
「はだしのゲン」連載開始40周年の企画展が計画され
中沢さんも出席される予定でした。
「困難に直面しても、たくましく生き抜いたゲンのように平和への道を切り開く力になってほしい。」と
原発の問題もみんなの取り組みが問われている今日です。
「原爆に負けてたまるか!」
車いすで酸素呼吸器姿で反戦を訴えてこられた中沢さん、
広島では今夏から平和教材の一つとして
「はだしのゲン」が使われるようになったとか、
あらためて、ゲンの姿から
中沢さんの思いに触れることができればと思います。
合掌
| タイガーマスク | 2012年12月23日 |
12月21(金)に
子どもたちにプレゼントと
文房具や柿を届けて下さる方がおられました。
丁度、下校中の小学生と正門で鉢合わせになったらしく、
子どもたちが「名前は?」と聞いたところ
「タイガーマスク!」とだけ言って白い車で帰って行ったと・・
荷物を受け取った子どもは
手提げ袋に入った文房具を持って教えてくれました。
・
最近はシャープペンシルを使う高学年の小学生も多く
鉛筆は意外と減らないのですが、
消しゴムやボールペンなどは予想以上に消耗の激しい文具です。
何気ないことかもしれませんが、
ちょっとしたことが
子どもたちの成長の糧になります。
ありがとうございました。
| 明日は冬至 | 2012年12月20日 |
12月21日は二十四節気の一つ「冬至」です。
昔から立冬からが冬と言われていますが、
本格的な寒さは冬至のころからです。
1年で一番太陽の力が弱い日で
「これ以上の陰が極まる日はないことから
転じて陽になる!」
と考えられたようですね。
一陽来福と結びつけて考えられてもいます、
欧州では太陽復活祭が行われるところもあるそうです。
日本ではゆず湯やカボチャを食べる風習がありますね。
寒い時期に体を温める食材を食べたり
ビタミンを補給しようとして行われていたのですが
健康管理の民間療法としては
理にかなっていたのかもしれません。
玉島学園では
水疱瘡が幼児さんに大流行中ですが、
皆さまも寒さ対策と健康管理にご留意くださいませ!!
ちなみに冬至の21日ですが
太陽の南中高度が最も低くなります。
夜が長くて昼がもっとも短いのが一般的な冬至についての説明ですが、
決して日の出の時刻が一番遅くて
日の入りが一番早くなっているわけではありません。
でも、冬本番を実感できる時期になっていることは
間違いありませんね(^^)
・
・
小耳にはさんだ蘊蓄
なぜ!ゆず湯
冬至と湯治
の語呂合わせという説もございます(^⋧^)
| 水疱瘡 | 2012年12月9日 |
先週のことですが
年少児で水疱瘡に罹患している子が出ました。
いま、2人の年少児さんが
飲み薬と塗り薬を使っています。
水泡のため、若干のかゆみを訴えているようですが。
二人とも、思ったほどの熱も出ず
食欲もあります。
ということで
本人たちは
室内でじっとしていることの方が大変なようです。
水泡が枯れるまでは、辛抱ですね。
| 師走 | 2012年12月1日 |
いよいよ12月
師走に入りました。
一般的には
普段は落着いている師(僧侶)も
年末は読経などに
忙しく走り回る月だからという説がいわれていますね。
雪の便りも聞かれるようになってきました。
寒さが厳しくなります。
健康管理に気をつけましょう!
なにはともあれ、
年神様を迎える準備を少しずつはじめておきましょう!
トイレやお風呂、
台所の油汚れなど、
時間と手間のかかるところを少しずつ・・・
・
・
・
ですよ。
| 岡山県要保護児童対策地域協議会関係職員研修会 | 2012年12月1日 |
11月30日
岡山県生涯学習センターを会場に
岡山県主催
岡山県要保護児童対策地域協議会関係職員研修会が
開催されました。
研修会は
「児童虐待死を検証する」と題した
小児科医でもある筑波大学人間系教授
宮本信也先生による講義を午前に
午後からは
事例提供を基に
グループワークを行いました。
岡山県内の児童虐待の防止に取り組んでおられる
さまざまな組織や団体から150名近くの方が
熱心に研修に取り組んでおられました。