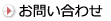- 2023年9月
- 2023年6月
- 2023年5月
- 2023年4月
- 2022年4月
- 2022年3月
- 2021年3月
- 2020年6月
- 2020年5月
- 2020年4月
- 2020年3月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2017年6月
- 2017年5月
- 2017年3月
- 2017年2月
- 2017年1月
- 2016年12月
- 2016年11月
- 2016年10月
- 2016年9月
- 2016年8月
- 2016年3月
- 2015年12月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年8月
- 2015年7月
- 2015年5月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年9月
- 2013年8月
- 2013年5月
- 2013年3月
- 2013年2月
- 2013年1月
- 2012年12月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月
- 2012年3月
- 2012年2月
- 2012年1月
- 2011年12月
- 2011年11月
- 2011年10月
- 2011年9月

| 全国司法書士会青年部法教育講座 | 2012年1月30日 |
1月28日土曜日
全国青年司法書士会主催の
法教育講座が開催されました。
岡山会場では、
岡山県司法書士会法教育委員会のスタッフ7名で子どもたちに話をして下さいました。
岡山県児童養護施設等協議会加盟施設の中から
5つの児童養護施設と1つの児童自立支援施設から
高校生17名、引率職員7名が参加し、
クレジットや悪質商法、
携帯電話、自転車のマナーやルールについて
学びました。
玉島学園では平成22年から継続的に
岡山県司法書士会法教育委員会のスタッフを中心に
法教育講座を定期的に開催しており
中学生以上の子どもたちは
学校や施設の決まりごとについての話をしたり、
保証人についてやキャッチセールス、マルチ商法などについても
学習してきていますが、場所や雰囲気が変わると
印象も変わってくるらしく、どの子も熱心に勉強していました。
・
・
乳児院を除く14の施設で90名近い高校生がいます、
今春巣立っていく子、
2~3年後に巣立っていく子さまざまだと思いますが、
少しでも多くの高校生が
ひとりで悩まないで相談するということを
忘れないでいてくれたらと、思っています。
| 岡養協県外施設視察研修 | 2012年1月27日 |
平成24年1月25日~26日の2日間にかけて
岡山県児童養護施設等協議会主催で
県外施設視察研修が行われました。
平成20年度の
鳥取県での視察から数えて
4回目の今年は徳島県の施設の視察に行きました。
ちなみに、岡山県児童養護施設等協議会とは
岡山県内12の児童養護施設と
乳児院、児童自立支援施設、情緒障害児短期治療施設の3つが加わった
15施設で運営されている組織です。
今回の視察には
児童養護施設10施設に
児童自立支援施設1施設の11施設で18名の参加がありました。
視察先は児童養護施設「徳島児童ホーム」
児童自立支援施設「徳島学院」の2施設です。
どちらの施設も、子どもたちの健やかな成長を願って
職員ができることは何かを考え、実行しようとしておられました。
改めて、話をうかがい施設の暮らしを垣間見ることで
私たちの子どもたちとの繋がりについて考えさせられた二日間でした。
お忙しい中、快く視察を受け入れて下さった
徳島児童ホーム
徳島学園の
諸先生方に衷心より御礼を申し上げます。
視察で得たことを今後の施設運営に積極的にいかしていこうと
心をあらたにいたしました。
| もうすぐ節分そして立春 | 2012年1月24日 |
寒い日が続いていますが、
あと1週間余りで節分、立春ですね。
今日はタイ焼きの差し入れがありました。
春を迎えるこの時期に子どもたちの成長を願って
子どもたちの役に立つようにと文具や志のプレゼントを続けて下さっています。
餅入りのタイ焼きは子どもたちにも大人気
幼児さんは温かいうちにと早速いただきました。
夜間高校に通っている子も
幼児さんと一緒に舌鼓を打っておりました。
幼稚園から上の子は午後のおやつの時間に
調理の先生に温め直してもらって、アツアツをほおばっていました!
・
書きそびれていたのですが、
17日にはSRSボクシングセッションでお世話になっている
坂本博之氏の倉敷のファンの方からぼたもちをいただきました。
鏡開きのお汁粉もそうでしたが、
アンコを好む子どもたちに、
素朴でいいなぁと思う
筆者でした。
| 大寒 | 2012年1月23日 |
1月21日は「大寒」でしたね
二十四節気の一つで
一年で一番寒い時期と言われています。
今年は大寒をはさんで寒い日が続きました。
皆さまはお変わりなくお過ごしでしょうか?
子どもたちは、
15日頃に体調不要を訴えている子がいましたが
全体的には落着いています。
中学3年生は入試間近なのに
余裕の毎日を過ごしています。
口やかましく言うのも逆効果と、
いろいろと策を講じる職員ですが・・・・・
| 左義長 | 2012年1月14日 |
正月の縁起物を燃やす、火祭り
小正月の行事の一環。
14日の夜か、15日の朝、
はずした正月飾りや書き初めなどを
お焚きあげします。
地方によっては、とんど・どんどという所もあります。
お焚きあげの火でお餅を焼いて食べることと、
お焚きあげの火にあたることで
無病息災を祈ります。
最近ではあまり見かけなくなりました。
学園も特別にお焚きあげをすることはないのですが、
平安時代から続く風習です、
気にかけておきたいと思いました。
・・
・・
そして、明日15日は小正月
豊作を祈り、ケガレを祓い清める日です。
小豆粥を食べて無病息災を祈る風習もあります。
ということで、
15日の朝ごはんは全員が少しずつですが
小豆粥を食します。
玉島学園としては、初めての試みです。
お粥の苦手な子も結構いますから、
子どもたちの反応が楽しみです。
| 鏡開き1.11. | 2012年1月11日 |
円満と繁栄を祈るならわし。
年神様へのお供えとして、
正月の間に飾っていた鏡餅を下げる日です。
雑煮やお汁粉にして食べることで
一家の円満と繁栄を祈ります。
正月に固いものを食べて歯を丈夫にし、
延命長寿を祈った「歯固め」の儀式と結びついています。
下げたお餅を刃物で切ることは縁起が良くないため
手で割るか、槌で砕きます。
この行為を「開く」と言います。
玉島学園では、お汁粉にしていただきます。
| 七草のうんちく | 2012年1月9日 |
1月7日は
五節句のひとつ人日(じんじつ)の節句
五節句は年中行事の中でも特に重要な節目を表す日です。
人日とは人を占う日と解釈され、
この日に春の七草という若菜で作った粥を食べて
無病息災を祈る風習が江戸時代に庶民にも定着したようですが、
実際は、7つの食材が全てそろうことは少なく、
手に入る数種類で作って食されたようです。
また、若菜は寒さに負けない強い生命力があると信じられ、
加えて冬場のビタミン補給にはうってつけの献立だったと考えられます。
今のような食材が豊富でない時代ですが、
生活の知恵は随所に感じることができます。
食材それぞれの薬効は以下の通り
せり:食欲増進、貧血
なずな:腎臓、肝臓の機能を整える
ごぎょう:せき、のどの痛みを抑える
はこべら:腫れや傷み
ほとけのざ:胃腸を整え、高血圧予防
すずな:便秘や成人病予防、葉の部分にはカルシウム・カリウムが豊富
すずしろ:消化吸収を高め、二日酔い予防
簡単に書いていますが、以上のようなこと
ひとつでも覚えておけば
今夜の小出しできる「うんちく」かな・・・
| 初詣 | 2012年1月8日 |
元旦。
学園で年越しをした子どもたちは、
元旦には近くの長尾神社にお参りに行きます。
秋のお祭りでは、千歳楽が参道に並び
露店も多くにぎやかですが、
初詣は静かな境内です。
子どもたちは、散歩がてらにお参りです。
受験生は合格祈願か?
2012年が穏やかな一年であるように。
・
・
・
そして1月5日には
吉備津神社に初もうで
毎年、学園で年を越す子どもらに
おそばを御馳走して下さる方が
せっかくのお正月だからと
別に心付けを子どもたちにいただくようになって
せっかくなので、一時帰宅していない子どもたちも
違った雰囲気を感じられればと、ちょっと遠出をさせていただきました。
昨年は最上稲荷
今年は吉備津神社にお参りに行き、
人の多さに圧倒されたようですが、
近場では味わえない雰囲気を味わうことができて、
大喜びでした。
| 昨日は小寒、今日は七草 | 2012年1月7日 |
1月6日は小寒(寒の入り)でしたね。
これから、寒さが本格化する時期です。
健康管理には十分注意したいですね。
長期予報では、
岡山県南部では晴れの日が多いものの
寒い日が続きそうです。
県北部では雪や雨の日も多いようです。
2月には雪遊び、スキーと楽しみな行事も待っています。
そして、
今日は七草、
年末年始で、ちょっと頑張りすぎたお腹に休憩です。
・せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ、
それぞれに、薬効が期待される食材です。
食品売り場で手軽に手に入ります。
節目の食事についても考えたいですね。
| 卒業生 | 2012年1月3日 |
年末年始の一時帰宅でちょうど半数くらい人数になる
玉島学園ですが、正月2日あたりは
別に申し合わせている訳ではないのですが
卒業していったOBたちが
元気な姿を見せてくれます。
お昼御飯を一緒に食べたり、
近況を話してくれる姿は頼もしい限りです。
昔話も出てきます、
「昔は、よう怒られよったよなぁ。」というのは、
必ず出ます。
彼女や、彼氏といっしょにくるOBも
結構多く、彼女なり、彼氏なりが
子どもたちと遊んでくれる姿はほほえましいですよ~